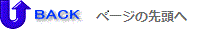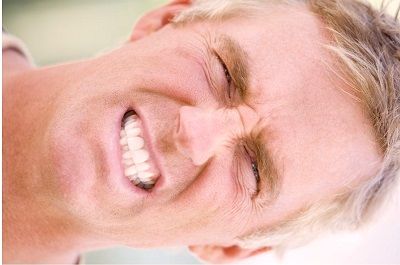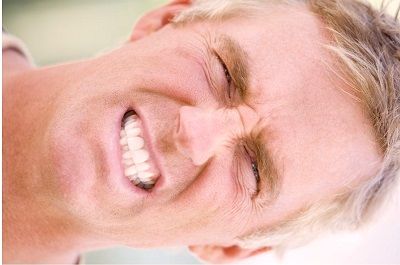
<お口のお悩みからみた原因と治療法>

12対ある脳神経の中で最も太い「三叉神経」により主要な歯科領域は支配されています。その情報伝達量が大きいという特性のため歯の痛みは激烈です。このページでは虫歯や歯周病の痛みの種類と原因、それと治療方法について解説します。
1.歯が原因


➀象牙質に限局する(軽度~中等度)の虫歯、あるいは歯と歯茎の境目の歯牙実質欠損
 チョコレート、アイスティー、冷水、ホットコーヒー、お茶、味噌汁でしみる!
チョコレート、アイスティー、冷水、ホットコーヒー、お茶、味噌汁でしみる!
 歯の表層は鎧に当たるエナメル質に覆われています。象牙質はその内側にあります。顕微鏡的には上図のような象牙細管が無数に存在し、各細管の最深部には知覚神経の末端が入り込んでいます。
歯の表層は鎧に当たるエナメル質に覆われています。象牙質はその内側にあります。顕微鏡的には上図のような象牙細管が無数に存在し、各細管の最深部には知覚神経の末端が入り込んでいます。
また、細管内には象牙細管内容液(水分)が満ちていて、その内容液(水分)が接触や冷水・温水など温度変化、甘味、酸味で容易に移動します。つまり内容液の移動が神経末端部を刺激し痛みを発するのです。
一般的に象牙質に限局する(軽度~中等度)の虫歯、あるいは歯と歯茎の境目の歯牙実質欠損場合は歯面に直接刺激を加えなければ痛みはありません。
 象牙細管の封鎖
象牙細管の封鎖
アイスキャンディーでしみる程度のエナメル質に限局した初期虫歯の場合は菌に犯された象牙質の除去後にコンポジットレジン充填(白く硬い歯の色をしたプラスチック)を行います。また歯頚部(歯と歯茎の境目)が楔形に欠けた状態のケースは歯を削らずにコンポジットレジン充填のみ行います。

歯ぎしりにより歯肉が下がって、歯頚部(歯の付け根)が露出しえぐれてしまっている。冷水にしみる状態。
歯頚部に殆ど欠損が認められずにただしみるという、いわゆる知覚過敏の際にはシュウ酸を塗布して歯のカルシウムと結合させシュウ酸カルシウムの被膜を作ってしみないようにする薬物療法を選択する場合があります。
②歯髄の手前までに達するやや深め(中等度)の虫歯

黄色矢印の先の白い部分は金属の詰め物です。その裏側に拡がる黒い影が虫歯菌に侵された部分です。

金属を外してみると中から黒褐色の虫歯が現れました。

冷たい物にしみる。時に甘い物にもしみる。この症状を放置すると温かい物にもしみるようになります。何も刺激を加えない時には無症状。

象牙細管を通って細菌が歯髄に侵入します。しみる症状が現れる際には歯髄組織1㎣に50個の細菌が存在するとの研究があります。
 このようなケースでは治療時に鋭い痛みを発するので、局所麻酔をした後に汚染された象牙質を削り取り、場合により歯髄を保護する薬剤などを塗布して症状が消えるのを待ってからコンポジットレジンまたはセラミックスで修復します。
このようなケースでは治療時に鋭い痛みを発するので、局所麻酔をした後に汚染された象牙質を削り取り、場合により歯髄を保護する薬剤などを塗布して症状が消えるのを待ってからコンポジットレジンまたはセラミックスで修復します。
➂歯髄に達する深い(重度の)虫歯

深い虫歯の存在

黄色矢印の先に出血点(歯髄露出)が認められます。歯髄の温存療法を試みましたが奏功せず、結果的に神経を抜く処置が必要となりました。

冷たい物、熱い物で強くしみて、その後30秒以上痛みが継続します。あるいは自発痛(何も刺激を加えなくても歯が疼くこと)が間歇的に起きます。就寝後に痛くなることや時に眠れないほどの激痛になることもあります。

歯髄内に細菌が多数侵入し、歯髄組織が炎症を起こしています。また壊疽が起こって閉鎖空間である歯髄腔に腐敗ガスが発生して内圧が高まって神経を圧迫します。

局所麻酔をしてから細菌感染した神経を取り除きます。稀に、歯冠部の神経だけを除去し、歯根部の神経を温存(生活歯髄切断法)する場合もあります。
④歯牙破折

痛くて噛めない、しみる、大きなひび割れの際は歯がグラグラする、何も刺激を加えなくても疼く、血の味がする。

神経を抜いてから10年以上時間が経過すると、歯がもろくなっていて硬いものを噛んだ時に歯が割れることがあります。また、就寝中の歯ぎしり、食いしばりが原因となっている場合も多く見受けられます。神経が残っている健全歯でも転倒などの事故で折れてしまうこともあります。


黄色矢印の先に亀裂が認められます。

抜歯してみるとご覧の通り歯根が割れていました。
垂直方向に割れてしまった場合は基本的に抜歯対象ですが、発症して数日以内でしたら一旦抜歯してから口腔外で歯科用接着剤を用いて貼り合わせ、もう一度植え直す(再植)することもあります。歯肉との境目付近で水平的に折れた際には神経を抜いてから差し歯にする方法が採られます。

2.歯周組織が原因
➀歯根膜の炎症

黄色矢印の先の黒い縁取りは歯根膜空隙の拡大=毛細血管の拡張を表しています。歯に対する強い荷重が原因です。

噛むと痛む。歯を叩くと痛む。何もしない時には痛みはない。時に冷たいものでしみることがある。

噛みしめ、歯ぎしりなどの悪習癖、被せたり詰めたりした修復物の噛み合わせの不調和

咬合調整、マウスピース(ナイトガード)の装着、食いしばりを減らすためのストレッチング、自己暗示療法。時に鎮痛消炎剤投与。
②根尖性(歯根の先端部付近)歯周組織炎

歯根先端部の骨が炎症性反応で溶かされて、黒い影(透過像)が出来てしまっているのが確認できます。

3年7ヶ月後、黒い影(透過像)が消失し新生骨が認められたので治癒と判定。根管の白く見える部分は消毒後に填入した封鎖材と薬剤。
 。
。
噛むと痛む。歯を叩くと響く。歯肉を押すと痛む。時に歯の付け根の歯肉が腫れ、何も刺激を加えなくても疼く。冷たい物、温かい物にしみない。

歯髄組織が死んでしまった際に根尖から細菌や壊死組織が漏れ出し、顎骨や歯根周囲にある歯根膜、歯肉に炎症を起こします。重症になると化膿して発熱したり、リンパ節が腫れることもあります。

根管内の消毒と症状消失後の根管封鎖。抗菌剤の服用。膿の多い場合は歯肉を切開することもあります。
➂辺縁性(歯の付け根の歯ぐき)歯周組織炎
親知らずの痛みなどもこれに該当するケースが多いです。

歯を支える歯槽骨が吸収して歯がぐらつき始めています。

歯肉が痛い。腫れて赤くなっている。歯と歯肉の境目を押すと膿と血が出る。歯がグラグラする。

歯周ポケット内の悪玉菌が数を増し、なおかつ身体の免疫力が低下したことによる発症です。細菌はそれ自体が産生する糖タンパクで出来たバイオフィルム内に多数の菌種とともに共存し増殖しています。歯磨きや歯間ブラシなどの清掃を怠るとバイオフィルムは成熟し高病原性を持ち始め、善玉菌でも悪玉菌でもない日和見菌が小悪玉菌化し、急性炎症を起こします。また過労や体調不良が発症の引き金になる場合もあります。

急性期では抗菌剤、鎮痛消炎剤の服用。その後バイオフィルムの徹底除去。

3.筋肉が原因

上あご奥歯周辺が痛くなる。冷たい物、熱い物にはしみない。食後や起床時に痛くなることもあります。筋肉部分を強く押さえると痛む。

主に側頭筋、咬筋の筋肉痛、筋膜炎による疼痛で、放散性・持続性の痛み起こります。噛みしめ癖・歯ぎしりが引き金になることも多いです。

筋肉のマッサージ、ストレッチング、鎮痛消炎剤服用。なるべく顎を安静にする。症状が落ち着くまではやわらかめの食事を摂る。チューインガム禁止。頬杖禁止。

4.神経が原因
➀三叉神経痛

上顎または下顎の広範囲にわたるピリピリとした痛み~ナイフで刺されたような激痛まで多様。突発性で数秒~1,2分間続く。冷風に当たったり、洗顔、咀嚼で誘発されることが多いです。

脳内で血管が三叉神経を圧迫していることが原因。稀(数%)に脳腫瘍、多発性硬化症が圧迫原因である場合もある。
 脳神経内科/外科にて
脳神経内科/外科にて
内服薬カルバマゼピン(テグレトール)
神経ブロック
微小血管減圧手術
などの治療が必要です。
②帯状疱疹

片側の顔、顎のかゆみ、痺れ、軽い痛みが数日間続いた後、紅斑~水ぶくれを伴う激し痛みが出現する。時に口が開けにくくなることもあります。

水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)が原因で、水疱瘡(みずぼうそう)に罹患した経験がある人に発症の可能性があります。水疱瘡が治癒してもウイルスの一部が末梢神経の神経節に潜伏し、加齢や免疫力の低下している時期に再び活性化して発症します。歯科領域では顔面神経や三叉神経の分布領域になります。
 内科にて
内科にて
抗ヘルペスウイルス薬、鎮痛消炎剤の服用、神経痛の後遺症がある場合は神経ブロックが行われます。

5.ACS急性冠症候群(心筋梗塞/狭心症)の関連痛

みぞおち、胸痛、背中の強い痛み、肩~腕の放散痛、冷や汗、呼吸困難。時に顔面、顎、奥歯の痛み。

血栓が冠動脈を詰まらせることで起こる心筋の虚血、壊死に付随する疼痛。心臓の痛みは信号が心臓から脊髄を経由して脳に伝わり、痛みとして認識されますが、肩、腕、みぞおち、顔、顎など上半身の感覚神経も脊髄を経由するので痛みの信号の混信が起こって症状が広範囲に拡がることがあるとされています。

奥歯が痛く歯科を受診したが該当歯が見つからない場合は循環器内科受診を考慮。

6.心因性の痛み

様々な疼痛(不定愁訴)、しみる、噛むと痛む、何もしなくても痛む、顎を動かすと痛む、顎を押すと痛む等々。

身体表現性障害(疼痛性障害)、あるいはうつ病の関連症状。

歯科学的な異常所見が認められない場合は心療内科への受診をお薦めします。